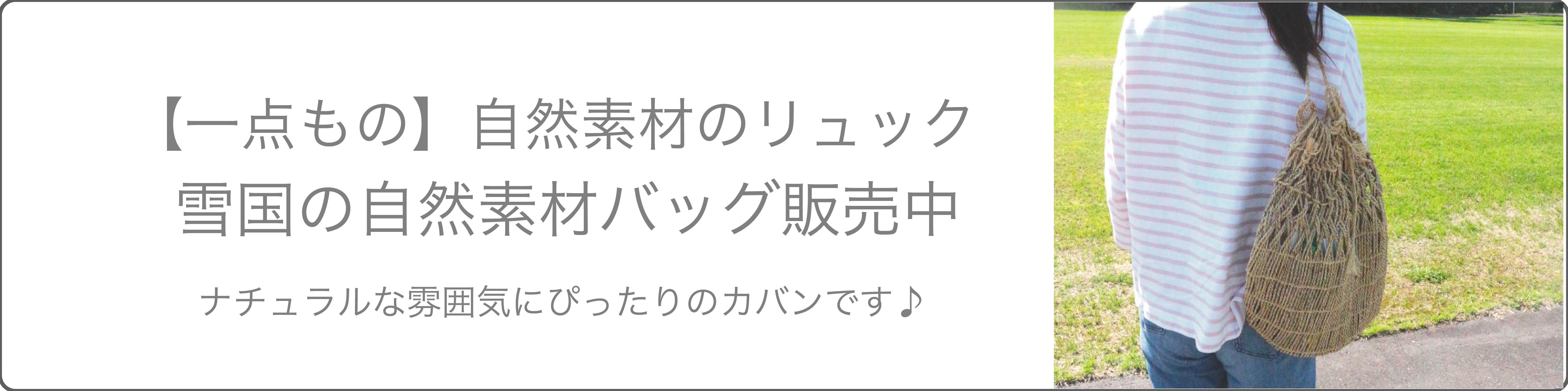仕事と暮らしの行き来だけじゃない。わら仕事がくれた、もう一つの居場所〜緑風舎/津南わら工芸会 松本文子さん 新潟県津南町鹿渡
2018.06.23
「移住」とは、暮らす場所を変えること。それは人生における一つの変化であり、一つの選択です。「移住」のきっかけは、人それぞれですが、移住女子たちに共通するところは、「移住」という一つの変化の中で、どう自分らしく、心地よく生きていくかに真摯に向き合っているところなのではないかと気付きました。
それでなくても女性は、結婚、出産、子育て、介護など、ライフステージの変化に心も体も環境も影響されやすいです。その分、しなやかであるけれど、悩むことだってたくさんあります。だからこそ、移住女子たちは、変化の中でも何を大切に生きていきたいのかがよく見えてくるのだと思うのです。
そんな移住女子たちのリアル、そしてしなやかさを、1週間のおわりにお伝えすることで、週末の時間にあなたにとっての「自分らしく生きる」を考えるきっかけになり、新たな気持ちで次の1週間に向かうことができたらうれしいです。
本業だけでもなく、暮らしだけでもなく、夢中になれること

第4話は、十日町市への移住を経て、現在は津南町で機織りを生業として暮らしている松本文子さんです。
松本さんは神奈川県出身、京都の芸術大学に進学し、染色や機織りを学んでいました。そんな松本さんがまず十日町市へ移住したきっかけは、当時同市にあった新潟県立十日町テクノスクール(旧 高等職業訓練校)で、さらに染色や機織りの技術を磨くためだったと言います。
そんな松本さん、いまでは娘さんからこんなことをよく言われるそうです。
「お母さんの本業はなに?」
なぜそんなことを言われるのかというと、染色、機織りと並ぶくらい松本さんが熱中していることがあるからです。
それは、わら細工。
「本職は染織だけど、私にとってわら細工はとても大事な一分野だよね。
わら細工のおかげで町に溶け込めたっていう感じもあるし」
そう穏やかな笑顔で語る松本さん。
松本さんを夢中にさせる、わら細工の魅力とはどんなものだったのでしょうか。
現在、津南わら工芸会の会長をも務める松本さんに、わら細工との出会いを中心に、移住生活についてお話を聞きました。
きっかけはひょんなことから。キーパーソンとの出会い

テクノスクールを卒業した後、松本さんは知人のいた津南町へ引っ越し。「緑風舎」として夫と共に染色と機織りを始めました。
そんな松本さんがわら細工と出会ったのは、当時行われていた地区運動会のある種目でした。
その種目というのが縄綯い競争。
縄綯い競争に出場した松本さんを見ていた地域の方が、「おまえさん、うまいね」と褒めてくれたのです。
そのときのことは、よく覚えていると話してくれました。
それからしばらくして、老人工芸展で並んでいたわら細工と再び出会います。
そこで、ある人物から声をかけられたのです。
その人物というのが、現在も津南わら工芸会でともに活動している師匠のお一人でした。
「今度わら細工の会を作るので、お前さんも参加しねえかい?」
そう声をかけてくれたことが、松本さんの転機になりました。
当時その方は、
「このままだとわら細工が絶えてしまうから、はつめ(*1)の者で寄って集まって、古くからの技術を掘り起こそうじゃねえか」
「適任者はいないか。いい人がいたら出るように言ってほしい」
と各地区の老人会に手紙を書いたそうです。
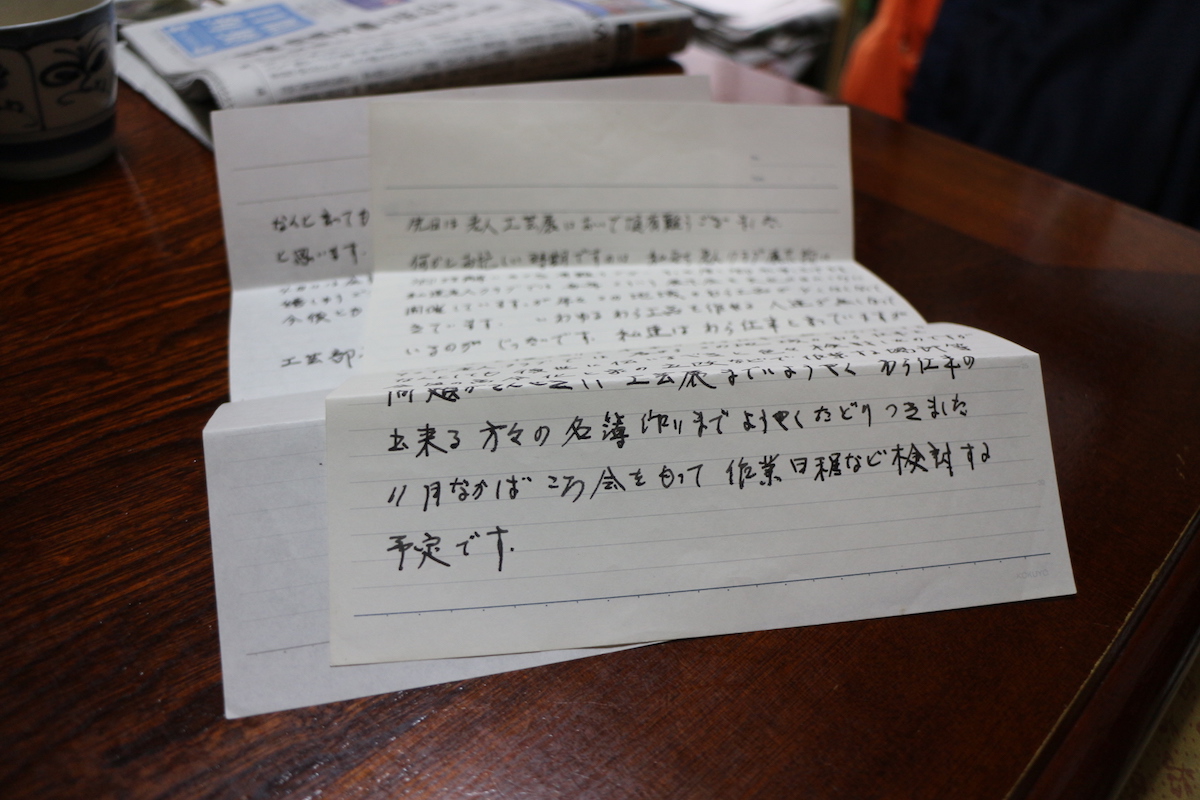
その思いに賛同し、各地区からやりたいという人が出てきて、津南わら工芸会が始まりました。
「当時はじっちゃんたちが25人くらい集まっていて。私と同年代の仲間二人がその隅っこでやっていたの」
それが平成13年。
今から17年前の出来事でした。
(*1)新潟の方言で、「器用な」という意味。
「習う」という受け手ではなく、能動的に会に関わる

そんな松本さんがこの会の会長になったのは、今から5年ほど前。
「会長は地元の人がなるほうがいいと思っていました」
わら工芸会に参加し始めたとき、松本さんは母校であるテクノスクールで講師の仕事をしており、興味のありそうな学生を会に呼んできたり、図書館などにチラシを置いたりと、宣伝活動を積極的にしていたとのこと。
そんな地道な活動も買われて、
「お前さん、外から人を連れて来るのがうまいすけ、会長をやってくんねかい?」と打診があったそうです。
それに対する松本さんの返答は
「みなさんが言うことを聞いてくださるならやります」
だったとのこと。
そう答えたのは、経験豊富な師匠方をまとめ、しかも次の世代につなげていかなくてはならない役目であると思っているからだと話してくれました。
職人であり、アーティスト

▲右が松本さんの作った「すっぺぞうり」
「私が会長になってから、『2.3日くらい実演会をしたい』と、師匠方に恐る恐るお伺いを立てたのね。わら細工って結構道具がいる。何日か続けてやれば、ちょっと面倒なものにも取り組めると思ったの。皆の技術のすり合わせもできるし、好きな曜日に来られる。外向けの宣伝にもなる。いいところがたくさんあるからやってみたかった。そしたら、じゃあ1週間くらいやろうかっていう話になって。え?そんなにやっていいんですか?って、びっくりしたことがあった」
わら工芸会では、「本物を作る」ということと同じくらい、「新しい視点」も大事にしていると言います。だからこそ、会の若手である松本さんの新しい意見にも、「やってみよう!」と取り組むことができたのでしょう。
「みんなが新しいことやってると、わあ〜って寄って来たり、『お前さん、これはどうやってやらんだい』って聞いてきたり、好奇心旺盛なところがあるんだよね」
そう語る松本さん、咋シーズンはセナコウジに挑戦したそう。
このセナコウジ、作る人によって少しずつ編み方が違うそうで、歴史民俗資料館などから借りてきたものを実際に見て、自分で編み方を考えながら作り上げたとのこと。

▲セナコウジ 荷物を背負うための道具。作る人によって、形や編み方も異なる。
わら工芸会の師匠方も、これには脱帽。
咋シーズンはセナコウジを工芸会の大先輩にも教えました。
「じっちゃんたちは、教わるって姿勢で聞いてくれる。90歳を前に、年下の私からこんな謙虚に教われるってすごいなって思うよね」
それだけ、師匠たちは柔軟に真摯に技術や知恵を磨いてきたということなのでしょう。
わら工芸会のメンバーは若手も師匠方も、謙虚に学び、好奇心を持って作る。職人であり、アーティストのようだなぁと感じました。
体験でも、講習でもない。相反するあり方が共存できる「工芸会」というかたち

松本さんは、ここ数年、「わら工芸会」のあり方についても、どうあるべきか思いを巡らせているという。
「体験はできないのか」
「講習会をしてほしい」
そんな声が上がることもある。
「伝統技術がそのまま伝わっている。それも大事なんだけど、ここは新しいものを作っている人がいると、どんどん変わっていく。そういう雰囲気も大事にしているの」
「技術を生きた形でつないでいくこと」と「本や講習で学ぶ」ということは全然違うこと。
「わざわざ集まって話しながらやるのが、大事」
と松本さんは話します。

わらの話や昔の話をしながら、教えたり、教えてもらったりを繰り返しながら、同じ時間を過ごす。
その中で、だんだんと「こういうことか」と体感としてわかってくる。
だから、津南わら工芸会が大切にしている
「基本を大事に本物を作る」
「自分の作りたいものを作る」
この相反する2つが両立できるのかもしれません。
「わら仕事に関しては並行していていいんだなって思う」
と松本さんは語ります。
ある意味相反するような、この二つのこと、実は何かを学ぶ上で大事な視点ではないでしょうか。
心地よくいられる場所

と同時に、ここまでわら細工を続けてきた理由には、工芸として、技術としての面白さに加えて、もう一つ大事な要素があったといいます。
それは、移住してこの町で生きていく中で、「わら工芸会」が一つの拠り所になっていたからでした。
「じっちゃん達って結構あっけらかんとしていて、そういうのが心地よかったんだよね。
大変なことをさらっと流してくれたりもしたから。
祖父母と一緒に暮らしていなかったから、今そういうことを教えてもらっている感じなのかな」

松本さんも、わら工芸会の皆さんも、ただ単に「わら細工の技術」を残そうというだけで集まっているのではないのだろうと感じます。
わら仕事をしながら、寄り合って話をする、そんな居場所として、大事な機能を持っているのではないでしょうか。
松本さんにとっては、津南わら工芸会が「サードプレイス」のような心地よい場所だったのでしょう。
「わら細工」と聞くと、一昔前の技術として語られがちですが、松本さんのお話を聞いていると、どこよりもクリエイティブで新しい可能性に溢れている場所だなとワクワクしてきます。
そういった、「暮らし」なのか「仕事」なのか境界の引けない、一個人としてワクワクするようなものや場所が、松本さんの移住生活を支えてきた大事な要素のひとつなのだなぁと感じます。
私自身は、そういった場所を持っているだろうか。
そう改めて見つめ直すきっかけとなりました。
みなさんにとって、「暮らし」「仕事」以外のワクワクするものごとはなんですか?
「自分のしあわせ」を考えるヒントになるかもしれません。
(*1)自宅や職場とは別の、第三の場所。公園、クラブ、カフェなど。
■松本さんの作ったわら細工を、雪の日舎で販売しています!昔の技術を継承した、「ほんもの」で「新しい」わら細工、ぜひご覧ください。
お話を聞いた人

松本文子
1961年生まれ。神奈川県出身。1989年に新潟県に移住。現在は津南町鹿渡で夫とともに「緑風舎」として草木染め、機織りを生業とする。また津南町わら工芸会の会長を務め、わら技術の継承を目指す。わら細工のブログ「山と田んぼとわら細工!」も日々更新中。
諸岡 江美子
スノーデイズファーム(株)webディレクター/保育アドバイザー。1987年、千葉県船橋市生まれ。東京都内の認可保育園にて5年間勤務、その後新潟県妙高市にある国際自然環境アウトドア専門学校、自然保育専攻に社会人入学。津南町地域おこし協力隊を経て、現在はClassic Labとして独立。雪国の「あるもの、生かす」という生き方を研究している。編集者、エッセイスト。
関連記事
-
コラム 【週のおわりに、移住女子】
村でともに暮らす仲間と一緒に。「わたし」から始まる「まるけて」〜「里暮らしむすびや まるけて」代表・鑓水愛さん
2018.12.04
-
コラム 【週のおわりに、移住女子】
無理はしない。やらないと決める潔さで、自分なりの心地よさをつくっていく。〜NPO地域おこし 多田美紀さん 新潟県十日町市池谷
2018.08.10
-
コラム 【週のおわりに、移住女子】
失敗してもいい。つまづいて、また歩き出そう〜「波と母船」代表・屋村靖子さん 新潟県糸魚川市鬼舞
2018.04.19
-
コラム 【週のおわりに、移住女子】
「移住女子」から「農家ヨメ」へ〜滝沢加奈子さん 新潟県津南町赤沢
2018.03.24