第11話「嫁いだら、アイデンティティ喪失。自分らしさを取り戻すためには」新海智子さん/長野県川上村
2019.10.11
世代を超えて見えてきた、視点
「どうしたら、子育てしながら自分らしく働き続けることができるのだろうか」
そんな私たちの悩みからスタートしたこの特集。
第1話では雪の日舎の女性メンバーの座談会をお届けしました。その中でも、佐藤が小さな子どもを育てながら農業を続けていくにあたり、さまざまな壁や悩みにぶち当たったこと、いまもあり方を模索しながら働いていることをお話しました。
第2話からは、農業に携わる女性たちがどんな思いで、どんな工夫を凝らしながら、この雪国で農と子育てを両立してきたのか。
それぞれの年代別に聞いてみました。
今回お話を聞いたのは、「農業」に携わる女性でしたが、皆さんが共通してお話してくださったことからは、直接「農業」に関わっていなくても、どんなお母さんの心にも響く大事な視点だったなと感じています。
まずはすでに子育てもひと段落した、先輩お母さん世代に当時の女性の働き方と子育てのサポートについてお聞きしてきました。
第2話 「季節保育園ってなに?」農家の暮らしに合わせたサポート〜水落静子さん/新潟県十日町市
第3話 母のあり方に人が集まる「農業も子育ても、おおらかに」福嶋恭子さん/新潟県十日町市
第4話 働きたい思いを叶えてくれた地域。だからママ農家の「ほしい」ものを代弁してゆく〜笠原尚美さん/新潟県阿賀野市
第5話 母として、仕事人として、まっすぐな想いが人の心を動かす〜農プロデュースリッツ 新谷梨恵子さん/新潟県小千谷市
続く第6話からは、現役子育て世代のお母さんたちに、今日までの葛藤や工夫を含めたリアルな心境をお聞きしてきました。
第6話 夫婦で移住。公共サービスをフル活用することへの期待と葛藤〜宮崎綾子さん/新潟県津南町
第7話 矛盾してたっていい。「いま」に合うかたちは変化し続ける〜宮原由美子さん/新潟県十日町市
第8話 「家族だけ」は意外としんどい。いろんな人の手が加わって、作物も子どもも育っていく。〜嶋村真友子さん/新潟県十日町市
第9話 田んぼでファミサポできますか?農ある暮らしのそばで子育てしたい〜佐藤佑美さん/新潟県長岡市
第10話 農家だからできる子育ての可能性〜髙橋真梨子さん/新潟県十日町市
第11話では、長野県川上村で家族と農業を営む新海智子さんにお話を聞きました。
農家の女性たちに話を聞いていくなかで、いかに自分らしいバランスで仕事(農業)、暮らし、子育てをブレンドしていくかは、その人が調整できる余白を持っているかによるのではないかという気づきがありました。
そのときに、私たちの頭に一番に浮かんだのが、新海さんでした。

新海さんは元々は埼玉県出身。都会で働いていましたが、結婚を機に旦那さんの地元である長野県川上村に移り住み、専業農家の嫁としての日々が始まりました。
現在は川上村内の女性たちでマルシェを開催したり、NAGANO農業女子として活動したりと農業に携わる女性たちが自分らしく生きることをテーマに活動もされています。さらに最近は、農業女子や地方の女性がFITした暮らしを創るためのサポートをする準備もしているようです。
そんな活動的に見える新海さんですが、実は以前は外に出るのも嫌になるほどだったと言います。
農家の嫁になり、「自分らしさ」がわからなくなるなかで、どのようにして再び「自分らしさ」を取り戻していったのか。
そして、周りの女性たちとつながっていったのか。
きっとそこには私たちの求めているヒントが詰まっているのではないかと、お話を聞かせていただくことにしたのです。
「わたしはただの家政婦?」嫁いで感じた疎外感

新海さんは「好きになった人が、たまたま農家の後継ぎだった」という理由で、農家の嫁になりました。
悩んだ末に旦那さんについていくことにした新海さん。
嫁いだ当初の思いはどんなものだったのでしょうか?
「嫁いですぐは、慣れるまでに大変だからと、畑は手伝わずにごはん作りを任されていました。
でもこれが、実はすごい疎外感がありましたね。私は畑の話もわからないし、友達もいないし、それはそれですごく苦しかったです。
貢献していないことが辛くて。ここは農業女子の問題だと思うんですけど。お金を生み出していないことに対して自分でも誇れない、貢献意欲が満たされないんです。家事や子育ても大事な仕事のはずなのに、畑よりはずいぶんと軽視されがち。ただの家政婦だって思っていた時期がありましたね」
「手がかかるのはいっとき」でも辛いのは「いま」なんです

お子さんが生まれ、家事に育児が加わり、さらに日中に少しずつ畑にも出ていった新海さん。
ある日突然、元気に働いていた義母が体を痛めてしまい、急激に暮らしが変わりました。
「夜1時から7時くらいまで畑に行って働いて、小学校の子どもを送り出して、家事、下の子の育児やって、また畑に戻って……限界でしたね。
川上村では『未満児は家で育てることがいいこと』というようなイメージが強く、私は保育園にも預けづらかったんです。
なんのために働いているんだろう?って思ったこともあります。
子どものためにって思って働いているのに、子どものためになっていないのではないかという気持ちにもなって。
夫は小さい頃からそういう家庭で育っているので、『俺もそうだったけど、大丈夫だよ』って。でもわたしは子どもがそばにいてほしいってときは、一緒にいてあげたかったんです。
そういうズレを埋めることが当時はできていなかったと思います。
『子どもはすぐに大きくなる。手がかかるのはいっときだけ』とよく言われますが、それって言っちゃダメだなって最近よく思うんです。
だって『いま』をどうにかしたいんですよ。
困っているのは『いま』なんだから。」
新海さんのそのことばにハッとしました。
「子育てはいっときだから」
確かにそうかもしれない。
でも「いま苦しんでいる人」にとって、それは「いっときなんだから、我慢せよ」と言っているようなものなのかもしれません。
考え方を変えたのは「学び」のちから

そんな新海さんが、苦しい時期を乗り越えて、現在の活動につながるきっかけはなんだったのでしょう?
「学びに行ったことかな。自分じゃもうどうにもならないから、人の視点を借りてきたということですね。
東京まで講座を受けに通っていました。東京まで行っていっぱい村の不満を言って。それをじゃあ次こうしようかなって案を持って帰って、やってみて、その繰り返しで少しずつ。
周りの人や村は一つも変わらないけど、自分の見方と行動でこんなに快適な場に変わるんだなって実感しました。」
そうして少しずつ少しずつ自分の周りの環境も変えてきた新海さん。
「わたしが変われたんだから、みんなも絶対変われる。」
そう力強く答えてくれました。
女性が自分らしく、生き生きと暮らすために必要なこと
新海さんのお話から、次の2つが重要なのではないかと発見がありました。
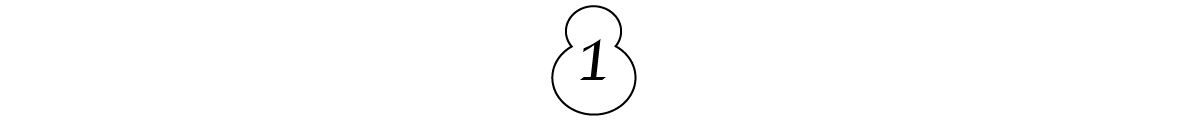
安心して「自分」でいられる場

これは新海さんが携わる「新米お嫁ちゃん会」がまさにその典型だなと感じました。
この「新米お嫁ちゃん会」は、結婚して5年目くらいまでのお嫁さんが参加できるワークショップ。
お局さんを入れないのは、「10年経てばなんとかなるよ」という意見が欲しいわけではないからなんだとか。
「お嫁ちゃんって、自分だけ鬼嫁なんじゃないかとか、自分だけがダメなんじゃないかって自己否定に入ってしまうんですよ。周りはキラキラして見えますしね。
でも、そんな人たちが安心が確保されている場を設定して話すことで、みんなもそうなんだってところでパワーも湧いてくるんです。
お嫁ちゃん会では大それたことはしようとか思ってなくて。『わかるわかる!』とか、『いいお店知ってる?』とか、そういう話でいいんです。出会うきっかけにして欲しいんですよね。
誰だっていい嫁になりたいし、可愛い妻でいたい。
そう思ったら、どこにいても安心できないと思うんですよ。
だからお嫁ちゃん自身が『私でいられる場所』が必要だと思うんです。
共感ベースで安心できる場を作りたいんです。」
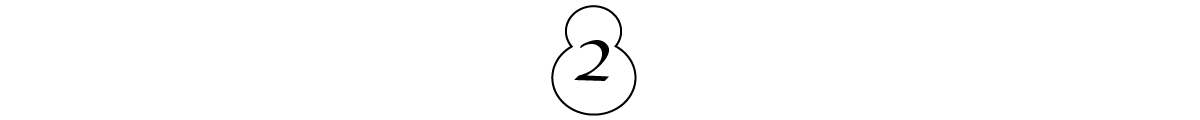
貢献意欲が満たされる場

「安心して自分でいられる場」である「新米お嫁ちゃん会」がお嫁さんたちの場として育っていくなかで、辿り着いた一つの形が「Kawakami Girls Collection」というマルシェでした。それが「貢献意欲が満たされる場」となったのです。
「村のお嫁さんて全国各地から来ていて、前職がバラエティに富んでいるんですよ。資格とかもたくさん持っているんですけど、村の8割が専業もしくは兼業農家の農村なので生かす場がないんですね。
まずは村で楽しめることで、みんなの特性を生かせるものをリストアップしたいねって言ってたんですけど『もうやっちゃおう!』ってなって。
その頃、村の女性活躍推進でアイデアコンテストとかやっていて機運もあったのかもしれません。今までは人の目を気にしていたけれど、私もなんかやらなきゃって勇気がぶくぶく湧いてきちゃったんですよね。
わたしの願いとして、村のなかで女性が人に直接貢献して、何かワンコインでもいいから頂く行為で、自分への自信を取り戻してほしかった。マルシェをやるにあたって、他の地域から作家さん連れてこようかっていう話も出たんですけど、それは絶対ダメって言ったんです。やりたくないって。村の人が今すでに持っているもので発表して、村の人が喜んでくれるものがいい。だってその時はまだ気づいてないけれど、女性達はもうすでに素敵なんですもん。村の人による村の人のマルシェにしたかった。
一番はお客さんに村の女性がこういうことしていいんだって伝えたかったんです。

やってみたら、出店者がどんどん変わっていったんです。パートナーシップがよくなったとか、周りの目が気にならなくなったとか、もっと繋がりたくなったとか。自信を取り戻し再び輝き出すにはとてもいいきっかけだったと思います。
今までマルシェは3回開催したんですけど、他のイベントにも出店するようになったりして。この冬には他の女性が手を挙げつぎのステップへ進みます。近隣のお店も呼んで大きなマルシェが行われるんですよ。
きっかけとつながりがあれば変化していくんだなって。いろいろ言われてると思うけれど、自分を表現するのって楽しいねと思えるようになったと思います。」
「カラフル農業女子」を発信したい。

そんな新海さんがこれからしたいこと、それが「カラフル農業女子」を発信することです。
「多様性があっていいってことを発信していきたいんです。農村や農業界では多様性が認められにくいと思っていて。嫁はこうゆうもの、女性はごはん作るもの、地域ではいい子でいることみたいな。
でも実際は、女性でも大きなトラクター運転している人もいるし、経営専門でやっている人もいるし、自分が楽しいこととか強みを生かしてやっている人とか結構いるんですよ。その反面『自分なんか』って思っている人がすごく多い。本来はそういう人も出てきてくれれば、農業がもっと多様で楽しく見せられるなって思います。
農業って男性社会だから、どうしても規模拡大とかバリバリ一人前にやりたいって気持ちになることもあるんですけど。
でも、暮らしも大切にしたいっていうのは、女性ならありますよね。自己実現と普通の暮らしをすることって、同じ方向を向いているはずなのに相反しちゃうときがあるんです。マルシェとかも、もっとやろうと思えばできるけど、暮らしに余白も必要だよねって最近はよく話しています。」
子育てや暮らしも大事にしたいからこそ、今までの「農業」のイメージに当てはめていくと、自分のしたいことがわからなくなるのかもしれません。
いろんな農業のかたちがあっていい。
そんな新海さんたちの発信は、多くの女性農家さんたちの勇気になるのではないかと、今までお話を聞いてきた農家女性たちの姿も頭に浮かびました。
自分だからできることで、アイデンティティを取り戻す

「自分のアイデンティティってなんなんだろう?ってことが大事かな。お嫁ちゃんって、一度このアイデンティティがなくなっちゃうんですよね。
わかりやすい例でいうと、自分の名前で呼ばれなくなるじゃないですか。『〇〇さんちの嫁』って。それってすごいアイデンティティの喪失で。今までの自分を否定されているような気持ちになるんですよ。
だから、自分のアイデンティティを回復することが大事。そのために『安心して自分でいられる場』と『貢献意欲が満たされる場』が必要なんだと思います。
結局は『自分ってなにが好きなんだろう?』っていう、自分自身が喜ぶポイントを見つけちゃえばいいんだと思います。
わたしの場合、ごはん作りは嫁のしごとだから…と思ってしぶしぶしていたところがあったけれど、数年経つと見方も変わって来ました。
例えばお父さん今日疲れてるな〜ってときには、『今日はお父さんの好きなかぼちゃの煮付けにするね』ってモチベーションあげたりとか。そういうことって外注じゃできないじゃないですか。わたしは頑張る人をサポートすることが好きなんですよね。
これがわたしのアイデンティティ。
そういう小さなところでいいので自分が喜ぶポイントを生活に増やしていくことが、生きがいに繋がるのかなっていまは思います。」
やっていることは同じことでも、自分自身の見方によって、自分らしく取り組めることがある。
新海さんのエピソードはまさにそれでした。
自分がもともと持っているアイデンティティを取り戻す。
そのために必要なことを、新海さんからは教えてもらいました。
新海さん、ありがとうございました。
お話を聞いた人
新海智子さん
農家/KURASHI FIT PROJECT 主宰/講師。1979年生まれ。埼玉県出身。結婚を機に、夫の地元・長野県川上村に移り住み農家の嫁になる。2人の子どもを育てながら、大規模農業を家族と営む。川上村女性応援チーム「WAO!」やNAGANO農業女子、農林水産省農業女子PJのメンバーとしても活動する。
FACEBOOK https://www.facebook.com/tomoko.shinkai
Note https://note.mu/tomokoshinkai
諸岡 江美子
スノーデイズファーム(株)webディレクター/保育アドバイザー。1987年、千葉県船橋市生まれ。東京都内の認可保育園にて5年間勤務、その後新潟県妙高市にある国際自然環境アウトドア専門学校、自然保育専攻に社会人入学。津南町地域おこし協力隊を経て、現在はClassic Labとして独立。雪国の「あるもの、生かす」という生き方を研究している。編集者、エッセイスト。
関連記事
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第12話 共感、変化、小さな一歩……農業女子たちのインタビューを終えて、雪の日舎女子のつぶやき
2019.12.13
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第10話 農家だからできる子育ての可能性〜髙橋真梨子さん/新潟県十日町市
2019.10.07
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第8話 「家族だけ」は意外としんどい。いろんな人の手が加わって、作物も子どもも育っていく。〜嶋村真友子さん/新潟県十日町市
2019.09.13
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第9話 田んぼでファミサポできますか?農ある暮らしのそばで子育てしたい〜佐藤佑美さん/新潟県長岡市
2019.10.04
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第7話 矛盾してたっていい。「いま」に合うかたちは変化し続ける〜宮原由美子さん/新潟県十日町市
2019.09.20
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第6話 夫婦で移住。公共サービスをフル活用することへの期待と葛藤〜宮崎綾子さん/新潟県津南町
2019.09.16
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第5話 母として、仕事人として、まっすぐな想いが人の心を動かす〜農プロデュースリッツ 新谷梨恵子さん/新潟県小千谷市
2019.06.24
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第4話 働きたい思いを叶えてくれた地域。だからママ農家の「ほしい」ものを代弁してゆく〜笠原尚美さん/新潟県阿賀野市
2019.06.21
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第3話 母のあり方に人が集まる「農業も子育ても、おおらかに」福嶋恭子さん/新潟県十日町市
2019.06.14
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第2話 「季節保育園ってなに?」農家の暮らしに合わせたサポート〜水落静子さん/新潟県十日町市
2019.06.10
-
特集 【くらす、働く、子育てする、里山の女性たち】
第1話「子育ても仕事も、どっちも充実させたい。それってわがまま?」〜ある日の雪の日舎女子会
2019.06.07




